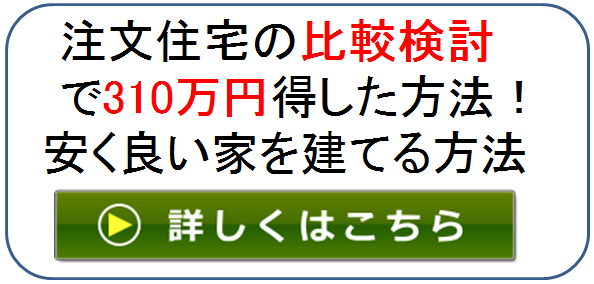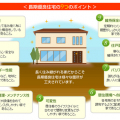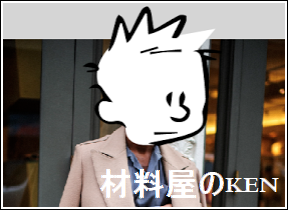増税によって大きく影響を受けるのは、マイホームや車などの大きな買い物です。とはいえ、増税前に全ての人が大きな買い物を済ませる事はできません。
増税前に新築を建てておく方が本当に良いのか、資金計画や住宅ローン減税の仕組みなどを元に考えてみましょう。
このページの目次
平成29年4月1日に消費税は10%へ

平成26年4月1より、消費税が8%となりました。そして平成29年4月1日には10%に引き上げられる事が決定しました。
車や家電製品の大きな買い物はこれまで以上に慎重に行わなければならず、マイホームの購入もその1つです。特にマイホームは一生に一度の買い物ですので、増税を不安に感じている方も多いでしょう。
増税によって新築の購入額はどのくらい変わるのか
例として、土地代800万、建物代3000万円(工事代含む)の予算で新築を購入するとします。土地には税金はかかりませんので、消費税の影響を受けるのは建物代と付随する工事代のみです。
土地代800万円
建物代3240万円(うち消費税240万円)
計:4040万円
土地代800万円
建物代3300万円(うち消費税300万円)
計:4100万円
単純に計算すると、差額は60万円となります。
60万円もあれば水周り機器にオプションを付けたり、家電製品を新しく買い替える事もできます。金額だけを見ると少し勿体ないと感じてしまいます。
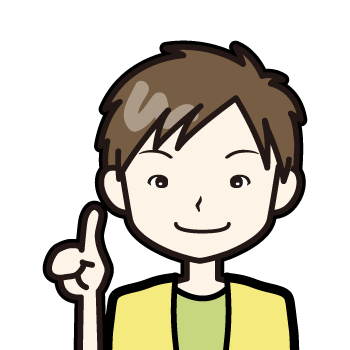
駆け込み需要に巻き込まれないよう注意
工務店やハウスメーカーには大量の見積り依頼が殺到すると予想されます。そのため、じっくり打ち合わせができなくなるばかりか、混乱による手配ミスなども考えられます。
また、リフォームの需要等も増えるため、大工の人手不足も予想されます。大工が手配できなくては工事が進まず、工事期間が延びて引き渡しが大幅に遅れてしまう恐れもあります。
「住宅ローン減税」を利用しよう
増税による負担を軽減するために、「住宅ローン減税」の枠が拡大されました。住宅ローン減税を利用すると、住み始めて10年間は所得税が控除されます。
以下の3つのうち最も低い金額がその年の控除額となります。
- 40万円(上限)
- 年末時点の借入残額×控除率(1.0%)
- 所得税(+住民税の一部)
枠の拡大前は上限が20万円となっていましたが、平成27年4月より40万円まで拡大されました。
(平成31年6月末まで実施)
借入額が2000万円を下回る場合は年間の最大控除額が20万円のままであり、枠拡大のメリットがありません。さらに、収入の低い人は所得税も低くなるため、控除額の上限拡大のメリットがありません。
このような不平を解消する措置として、以下の「すまい給付金」が新たに制定されました。
「すまい給付金」を併用しよう
住宅ローンの減税では増税後の負担が軽減されない場合は、「すまい給付金」を併用する事ができます。各種の条件を満たし、一定以下の収入であれば申請が可能です。
給付基礎額(都道府県民税の割額)×不動産持分割合=給付額
例:神奈川県の場合)
A:収入が450万円以下→給付基礎額50万円
B:不動産持分割合→100%
給付額=50万円
申請後、審査が完了すると給付額が指定した講座に振り込まれます。
現金で受け取れる点が大きな魅力と言えるでしょう。
(平成31年6月末まで実施)
収入やローン額によっては増税前と同額で新築を建てられる
新築を建てる時の条件は、収入や、ローンの借り入れ額、建てる家の規模などによって大きく変わります。
増税によって支払額は確かに大きくなりますが、住宅ローン減税やすまい給付金を確実に申請し、増税による増額を相殺できるような資金計画を立てる事もできます。
購入資金は必ずしも一括で支払うわけではない
総支払額だけで判断し、焦って新築に踏み切る事は非常に危険です。
総支払額は確実に支払わねばならない費用ですが、ローンの返済を考えると、増税前と後の月々の負担額は数千円程度の差です。そのため、増税によって返済額が大きく家計を圧迫する心配は少ないと言えるでしょう。
経過措置の期間に注意
新築の引き渡しが増税後の平成29年4月1日以降でも、工務店やメーカーとの請負契約を平成28年9月30までに交わしていた場合は8%のままの税率が適用されます。平成28年の10月以降に交わした契約の場合、経過措置は適用されません。
経過措置の適用
→増税の半年前=平成28年9月30日
まとめ
増税後に新築を建てる場合、費用が多くなってしまう事は避けられません。しかし、焦って建てたばかりに納得のいくプランにできなければ、これから長く住む家である事を考えると結果的に損をしてしまいます。
もし新築購入の支払いが増税のタイミングに差し掛かっても、減税や給付金を賢く利用し、今の生活に大きな負担とならない資金計画を立てておくと良いでしょう。